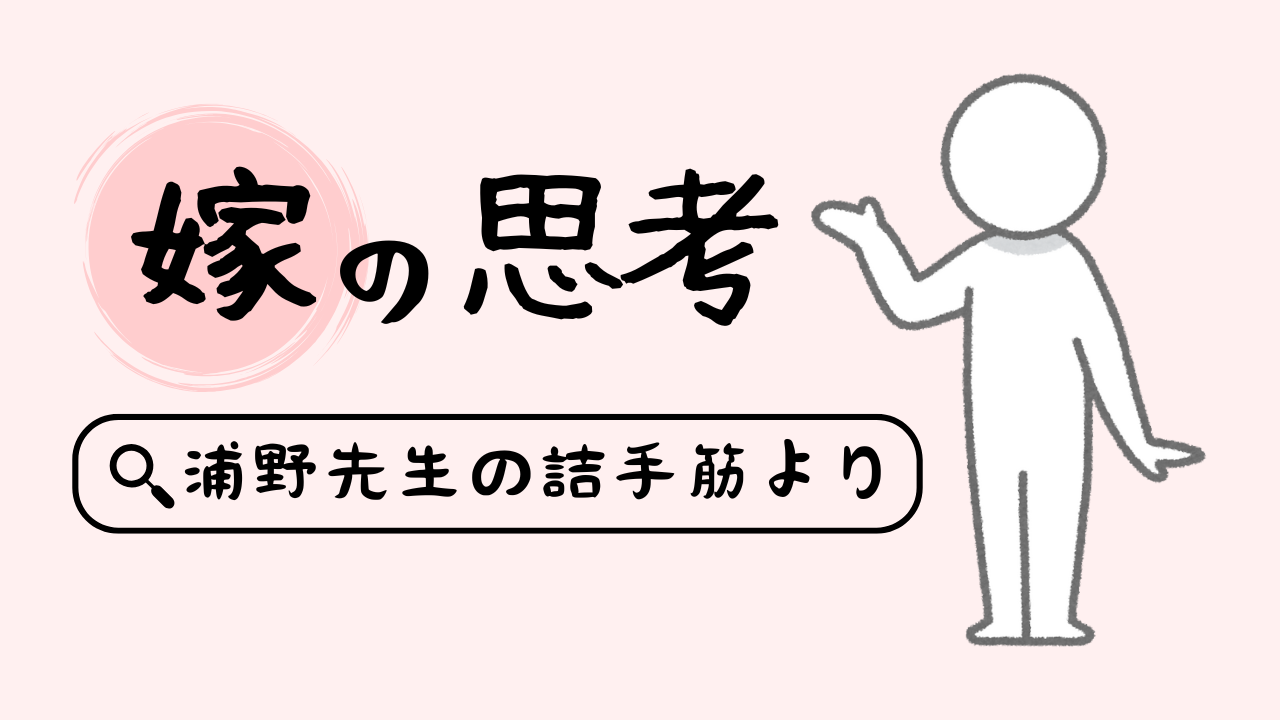はじめまして。springsの妻です。駒の動かし方を覚えたのは小学3年生のとき。指将棋は大学1年生から本格的に始めました。そのとき私のペースに合わせて教えてくれたのが旦那のsprings。大学を卒業してからはしばらく指将棋から離れていましたが、詰将棋創作を始めた旦那を見て私も詰将棋創作を始めました。なので創作歴は1年ちょっと。そんな私だからこそ伝えられることもあるのではないかと思って自分なりに活動しています。
さて、この記事は「浦野先生の詰手筋より」というタイトルにしています。浦野先生と言えばもちろんみなさんご存知プロ棋士の浦野真彦先生。その浦野先生が2018年に『詰手筋DVDブック』という本を出版されました。内容は初心者向けに詰みの形を説明しており、解説DVDもついています。私が注目したのはこの本の目次です。目次では詰手筋ごとに分類されているので、詰将棋創作のアイディア一覧になるなと感じたのです。指将棋をする人からすれば「頭金」は知っていて当然のものかもしれません。そして「頭金」の一手詰を作りなさいと言われれば難なく作れるでしょう。ただ、3手詰となったらどうでしょう?指将棋しかしていないころの私ならば「え?できるよ?」と簡単にとらえていました。ただ、実際に作れたと思っているものの多くには余詰が存在します。余詰という言葉は聞いたことのある人もいるかもしれませんが、変同という言葉は聞いたことがありますか?変化と変同、余詰の違いを明確に説明できますか?意外と知らないことが多いものです。実は私は未だにこの違いがインプットできず旦那を困らせています。
そこで思いついたのが今回の企画です。「浦野先生の詰手筋より」というタイトルで複数回に分けてテーマに沿った短手数の詰将棋を作ります。その中で私が困ったことや失敗したことを記事にしようと思いました。そして私はフェアリー詰将棋(変則ルールや特殊な駒を用いた詰将棋)も大好きなので、伝統ルールの詰将棋(一般的に知られる詰将棋)とフェアリー詰将棋の2つを作ろうと思います。まだまだ分からないことは多いので、有識者には改善点や間違っている点などを教えていただければ幸いです。
初回は先ほど取り上げた「頭金」の詰将棋をつくってみます。楽しんでいただければ幸いです。